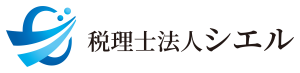取引の国際化・市場のグローバル化に伴い、中小企業であっても外貨建てで
商品や備品・機器を買ったり、物やサービスを売ったりする場面って意外と
多くなってきていますよね。

外貨建て取引!
何だか難しそう…と身構えなくても大丈夫です。
基本中の基本ルールというものが決められています。
売上や仕入・経費は「取引を行った日」の為替レートで日本円換算。
外貨そのものや売掛・買掛等の短期債権債務は期末レートで換算。
(※法人税法 第61条の8、第61条の9 より)
じゃあ何も迷わないじゃないか、と思いきや、経理の現場では
この原則ルールだけでは「乗り切れない」場面がいくつか出てくるのです。
今日は そのうちの代表例を2つ、ご紹介しましょう。
**~**~**~**~**~
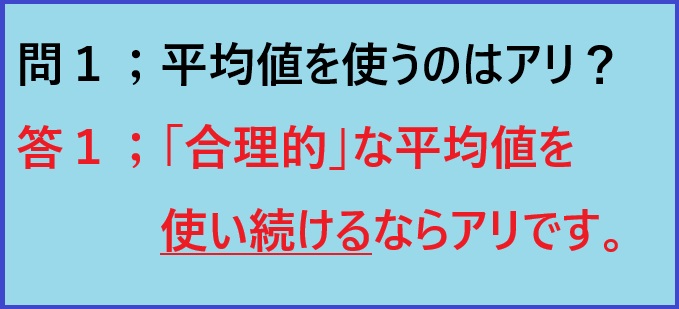
取引回数が多いから、いちいち「発生した日」をたどって調べるのが
手間かかってしょうがない!会計処理が進まない!
例えばそういう場合のための、特別ルールがあります。
(※下記、法人税法基本通達13の2-1-2、注書の2より抜粋)
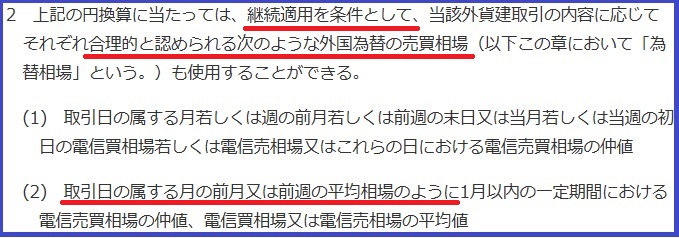
ちゃんと「平均相場」使ってもいいですよって、書いてありますね。
ただ、ここで注意したいのが「社内レート」という存在。
つまり、「うちの会社では外貨換算するときはこのレートで」と
社内ルールを設定している場合、わりとよく聞きます。
別に社内ルールとしての「社内レート」があってもいいんですが、
1ヶ月を超えて固定しているようなレートは税務上「合理的」とは
認めてもらえないので、そこは決算処理の時に実際レートとの
差額を計算・見直しを行いましょう!
(※参考;法人税法基本通達13の2-1-10 )
**~**~**~**~**~
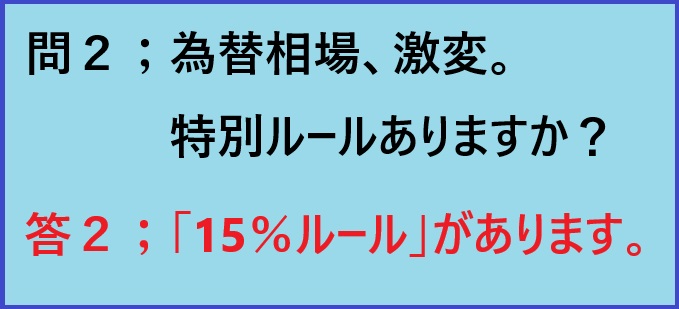
冒頭で申し上げたこのフレーズ、もう一度見てみましょう。
↓ ↓ ↓
売上や仕入・経費は「取引を行った日」の為替レートで日本円換算。
外貨そのものや売掛・買掛等の短期債権債務は期末レートで換算。
↑ ↑ ↑
これが原則ルールなんですが、例えば税務署に「届出書」を出せば
売掛金や買掛等の「短期の」債権債務についても、
決算年度末のレート(期末レート)ではなく、取引発生日のレートを
使うこともできるわけです。
それに、そもそも長期債務(例えば長期借入金)などは何も特別な
届出を税務署にしないかぎり、「発生時レート」で換算します。
で、その取引を行った日の為替レートで評価することになっている
債権・債務、つまり1年以上期日が先という未収入のもの・未払いのもの。
為替レートの変動が大きかったら、決算書に与える影響が大きくなります。
最近の相場(トランプ・ショック?)を見ると、ありえないことではないと思います!
(※下記、Wiseのサイトより)
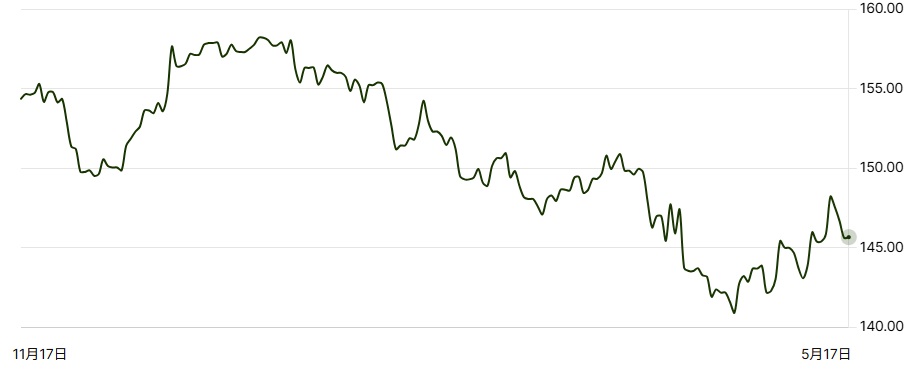
例えば、1ドル160円の時に発生した、USドル建ての長期借入金100,000ドル。
借りた時のレートで、決算書には「借入金が1,600万円あります」と表示され続ける。
でも、決算を迎えて年度末の日に見てみると、なんと1ドル135円になっていた!
もしそうなら、その借入金の「実際の価値」って、1,350万円ですよね?
決算書に書いてある「発生時の価値 1,600万円」で、年度末で計算してみた
「実際価値 1,350万円」との差額が250万円もある!
その「年度末での、実際の価値」×15% = 210万円
15%以上もその借入金の価値が変わった!
そういう時は、普段なら「取引発生日の為替レート」で決算書に
書きなさいってなっている債権・債務であっても、
為替相場がそんなに変わったんなら年度末レートで計算しなおした額で
決算書に書いていいですよ!という特別ルールがあるんです。
(※下記、国税庁サイトより法人税基本通達の引用)
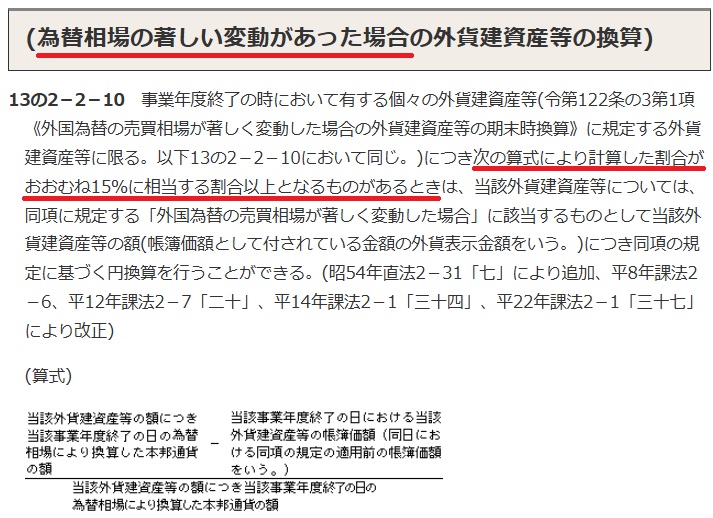
気を付けてほしいのは、ドル建ての長期借入金や未払金だけ年度末レートで
決算書の金額を書き換えておいて、同じ「ドル」建ての長期未収入金などは
発生時のレートのまま…という、「いいとこ取り」は出来ないということです。
**~**~**~**~**~
他にも色々な論点はありますが、今日は取り急ぎ、
「実務でよくある場面」をご紹介しました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
(^^)