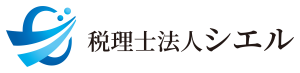皆さんこんにちは。あっという間に、もうお盆ですね…。
お盆といえば、亡くなった家族やご先祖様を偲ぶ季節。
かくいう私も、昼間はお墓参りに行っておりました。
それはそうと、ご家族を亡くされたばかりの方にとっては、
「相続にまつわる手続き」 が何かとわずらわしいものですよね。
私のような税理士は、そういった書類の整理や相続手続きの一部を
仕事として、お引き受けすることが多いのです。
よって、今日はそういった 「 相続にまつわる書類 」 の中でも、
こんな書類が届いたら、ぜひ税理士に相談して下さい!
という書類をご紹介しましょう。(具体的には、こんな書類です。)
↓ ↓ ↓

これ、書いてあること、皆さん理解できますか?
… いやいや、簡単にいえば
「 アナタのとこ、相続税かかるほどの財産あるんじゃないですか?
財産あれば税金計算して払ってね。なければないって返事してね。」
というお尋ねなんですけどね。一般人には分かりにくい言葉で書いてますよね。(^_^;)
ここはひとつ、私がざっくりと、分かりやすく解説してみましょうか。
まず、この出だしの部分。
↓ ↓ ↓
(もともとの文章)
ところで、お亡くなりになられた方の遺産の総額が基礎控除額を超える場合、
その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日
から10か月以内に、相続税の申告と納税が必要になります。
つきましては、他の相続人の方々へのご連絡の上、同封の
「相続税の申告のしかた」により申告と納税の必要があるかどうかを確認され、
次の1又は2に記載するところにより同封の「相続税の申告書」又は
「相続についてのお尋ね」を提出して下さい。
↓ ↓ ↓
(私が思い切って普通の言葉にしてカンタンにまとめた文章)
ところで、亡くなった方の遺産の金額が、法律で決めた一定の額を超えるほど
ある場合は、「相続税」 という税金を払う手続きをしないといけません。
(その手続きの締め切りは、亡くなられた日の翌日から10か月以内です。)
つきましては、その遺産をもらう権利のある方が他にもいる場合には
その人達に連絡してください。
そして、この書類とセットにしてお送りしている「相続税の申告のしかた」
というマニュアルを参考に、ホントに自分達は相続税の申告手続きをしないと
いけないのかどうか確認してください。
その確認をしたうえで、ホントに相続税の申告手続きをしないといけない人は
相続税の申告書を提出して下さい。
確認した結果、実は相続税の申告手続きは必要なかった!という人は、
「相続についてのお尋ね」 という書類の方を提出して下さい。
…伝わりましたかね。(^_^;)
そうそう、「亡くなった方の遺産の総額が、法律で決めた一定の額を超える」
というのは、どういう時なんでしょう。
これ、ちゃんと書いてあります。(クリックで画像を拡大できます)
↓ ↓ ↓

見えますか?
5,000万円+1,000万円×法定相続人数
法定相続人数っていうのは、要するに遺された家族の人数。詳しくは
「遺産をもらう権利があるよ、と法律で決められた人の数」 です。
ご主人が亡くなって、奥様とお子様3人なら、9,000万円ですね。
その9,000万円を超える額の遺産があれば、相続税を払うべく、手続きしないと
いけないってことです。
ここで一つ、大事なこと。
平成27年1月1日以降に亡くなられた人の場合。
この「法律で決められた一定の額」は、5,000万円+ ~ じゃないですよ。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 に変わります!
世の中、相続税の心配をしなきゃいけない人が増えるんですよね…。
そういう時は、ぜひ、私たちのような税理士へ相談して下さい。
相談するだけ、遺産がどのくらいの計算になるのか確かめてもらうだけ…なら
そんなに高くつきませんから。
ではでは、今日はこの辺で。(#^.^#)